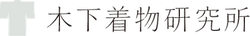「和裁の基本」 『難しいを難しくないに!』Vol.3 【女将紅子コラム】

月に一度、女将紅子が仕立てや和裁の基本、
『難しいを難しくないに!』をモットーに、
第3回目は
「和裁の基本 」
をお届けします。どうぞ最後までご覧くださいませ。
わたくしは、和裁についての知識は、2つの側面があります。
①着物の仕事を通じて身についた知識
(着物の仕事は18年ほど従事しております!)
②和裁について実際に縫うことを通して学んだ知識
(1年間毎日終日休まずみっちりと学びました!)
そして、着物着用者としての悩みを解決させるべく、自分で学びを進めて得た知識もあり、これらを活用して日々仕事をしております。
今回は、着物の仕立ての前段階となりますが、和裁の基本についてお伝えします。
↑和裁になくてはならない、コテ(アイロンのように使います)
今後仕立てについて疑問点があった場合、和裁についての基本がわかっていると、より深く理解していただけることと思います!
和裁の基本、
特徴と言い換えましょうか。
・デザインがない
着物は、基本的な形が決まっており、基本的な縫い方も決まっています。
裁断の際は型紙は使わないのです。
寸法と裁ち図と言われる図解的なものを使い、直線で裁断します。
(数字に強くないと大変!!)
・左右対称
検品をする際、左右同じかどうか様々な箇所で確認!
(和裁を習っていた際、先生によくご指導いただきました…)
洋服は左右が対称でなくても構わないと思いますが、着物は×
理由→左右非対称ですと畳めないということに!!
・基本的に平面的な縫いである (衿周りだけ少し立体的に縫います)
体の線に沿った縫いではなく、直線的な平面的な縫い方に。
着物はなぜフラットに畳めるのか
→平面的な縫い方だからだとわたくしは理解しています。
洋裁のようなダーツがある着物があるとすれば→常のように畳めません!!
→このことは、着物は畳んで仕舞う衣服であることに繋がってゆきます。
・布を無駄にしない裁断
布の端切れも一部ありますが、ほぼほぼ四角形の形。
洋裁のような細かい端切れは出ません。
このことは、着物はサイズ変更することが前提の衣服であることに繋がってゆきます。
・サイズ変更を見越した縫い方
余った布は中に縫い込んで、将来的に寸法変更が出来る縫い方をします。
縫い代の幅も一定ではなりません。着物の幅、着用者のサイズによって異なります。
このことは、着物はサイズ変更することが前提の衣服であることに繋がってゆきます。
この特徴を洋裁と比較してみましょう。
・デザインがあること
・型紙を使って布を裁断すること
形が様々な布の端切れが出ます。
・曲線裁ちで体のラインに沿って仕立てること
バストライン、ヒップライン、ウエストライン、など曲線で裁血、縫いでもダーツなどが入り、より体にフィットさせることができます。

↑左から 竹の物差し(センチではなく尺貫法!)
布を引っ張り縫いやすくする「かけはり」
布に印をつける「へら」
コテも含めて実際に紅子が和裁を学んでいたときに使っていたものであり、本日現在も使用しています。
和裁、洋裁、それぞれの違いをお捉えいただくと、
和裁の特徴がより鮮明にご理解いただけるのではなないでしょうか?
この特徴をご理解いただくと、着方の悩み等の理由が理解できることも。
何においても理解することって大切ですよね。
今月のコラム、いかがでしたか?
着物を楽しむ上でお役に立てたら嬉しいです!