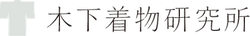2025年 4月 10日コラム
「手染めの帯揚げの工程」 『難しいを難しくないに!』Vol.4 【女将紅子コラム】

月に一度、女将紅子が仕立てや和裁の基本、
『難しいを難しくないに!』をモットーに、
第4回目は
「手染めの帯揚げの工程 」
をお届けします。どうぞ最後までご覧くださいませ。
時折、お客様からご質問をいただきます。
「帯揚の端にあるポツっとした色が濃くなっていて、穴が空いたような跡のようなものは何でしょうか?」

これは、手仕事で染めを施した、’引き染め’という技法で染めた証です。
手仕事で帯揚の生地を染める場合、
「伸子張り」という方法で生地を張ります。
この竹ヒゴで刺したところに染料が溜まりやすくなります。
一定の間隔で布の端の部分にホールが発生し、その部分の色が濃くなります。
この伸子張りを行う時は、
伸子針という竹ヒゴの先に針がついたものを用います。
生地の端を刺し、生地をピンっと張らせます。
↑伸子針
生地の端を刺し、生地をピンっと張らせます。
↑伸子張りを行なった生地を裏から撮影したもの。
伸子針の使い方、そして張った状態が分かりやすい画像です。
※今回は浴衣を染めた時の工程の写真ですが、生地が変わるだけで方法は同じです。
なぜこのような工程を行うのか、それは生地を張ることによって、職人が刷毛を使って染めやすくなるからです。
↑伸子張りを行なった生地、実際にこの生地の面に職人が染めてゆきます。
↑職人が実際に生地を染めている途中。

↑染め上がった生地を裏から見た画像。
この竹ヒゴで刺したところに染料が溜まりやすくなります。
一定の間隔で布の端の部分にホールが発生し、その部分の色が濃くなります。
さて冒頭にご質問に戻ります。
「帯揚の端にあるポツっとした色が濃くなっていて、穴が空いたような跡のようなものは何でしょうか?」
さて冒頭にご質問に戻ります。
「帯揚の端にあるポツっとした色が濃くなっていて、穴が空いたような跡のようなものは何でしょうか?」

↑このホールの部分は、手染めである印でもございます。
この染め方は、’引き染め’と言って、帯揚げではあまり用いない、着物を染める際に
用いられる技法で、色が綺麗に上がります。
木下着物研究所は、色の綺麗さを求めて、この技法で染めることを選択しています。
色の綺麗さは’引き染め’が良いと思っておりますが、どうしてもコストが高くなります…
全ての帯揚が、’引き染め’で染められている訳ではございませんので、ホールができていない帯揚げも存在します。
この染め方は、’引き染め’と言って、帯揚げではあまり用いない、着物を染める際に
用いられる技法で、色が綺麗に上がります。
木下着物研究所は、色の綺麗さを求めて、この技法で染めることを選択しています。
色の綺麗さは’引き染め’が良いと思っておりますが、どうしてもコストが高くなります…
全ての帯揚が、’引き染め’で染められている訳ではございませんので、ホールができていない帯揚げも存在します。
帯揚といっても、様々な色柄のものがございます。
お気に入りで使っているものがどんな技法のものなのか、ちょっと気にしてみていただくことで、より着物ライフは楽しいものになるのではないでしょうか。
お気に入りで使っているものがどんな技法のものなのか、ちょっと気にしてみていただくことで、より着物ライフは楽しいものになるのではないでしょうか。