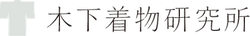「日本文化に触れるひとときを鎌倉で過ごす “茶の湯ワークショップ”」『今こそ“着物”』VOL.21 都田恵理子さん

食や美容などライフスタイルの分野で活動する都田恵理子さん(ローフード研究家)による暮らしと着物を愉しむコラムを月に1回お届けしています。
今回は、「日本文化に触れるひとときを鎌倉で過ごす “茶の湯ワークショップ”」をお届けしたいと思います。
先日、歴史や風土、豊かな自然に囲まれる鎌倉を訪れ、木下着物研究所でスタートした「茶の湯ワークショップ 〜鎌倉で武家茶道に触れる〜」に参加しました。
近隣にはよく知られた神社仏閣に隣接する位置にあり、築100年前という研究所を構える古民家が会場です。
建物に入ると出迎えてくれるのが、商家の雰囲気を残す開放的な玄関です。すると、明るい笑顔の女将の紅子さんが現れます。
「こんにちは、お越しいただきありがとうございます」。
この日は、ライブレッスンでお目にかかったばかりでさらに嬉しさが倍増し、まるでここでの毎日に溶け込んだかのようなこのようなアットホームな雰囲気に包まれます。

さて、ワークショップでは、茶室とテーブル席のある部屋とを移動し、武家茶道「三斎流」の教授者である代表の勝博さんが、季節の室礼とお道具の魅力を伝え、紅子さんによるお心入れのお菓子を体験することができます。
まず、茶室からスタート。「三斎流」のはじまりからや出雲のお家元のこと、その日の趣向を重ねた床の間の掛け物や竹花入れと庭の椿など、紅子さんお手製のお菓子に至るまで、初めてでも経験者でも楽しめるものとなっています。
勝博さんが一人一人に一服のお茶を点て下さって、伝統工芸の意匠が持つお道具の意味や解釈を聞きながら、自分の世界も広がり、参加者同士も交流が深まりました。

次に、テーブル席に移動して、日常の延長線にある卓上でのお茶の点て方を体験します。お盆を使用し、その上で点てるお茶は、生活の中で気軽にお茶をいただく機会になるとともに、安らぎを得ることやゲストをもてなすことができるそうです。
私も茶道を学んでいますが、特に自分の流儀と異なる所作に興味を持ちました。格式を感じる所作が残る点前を教わることで、お道具に触れる気持ちも新しく感じる体験でした。
初心の方や男性も茶道に触れることができるワークショップということもあり、ご一緒した方も楽しさとさらなる奥深さが増したとおしゃっていて、これからもっと茶道を学んでみたいと感じるのではないでしょうか。
勝博さんによりますと、今後も引き続き、移ろう季節とともに、武家茶道「三斎流」のお茶を体験していくことができるそうです。みなさまも鎌倉でお茶の素晴らしさを体験してみてはいかがですか。
※こちらのコラムは、毎月1回配信してゆきます。
【プロフィール】
都田恵理子(みやこだえりこ)ローフード研究家
オーガニック業界での広報職を経て、体にやさしい食や美容を専門に情報発信を手がける。madame FIGARO.jp などで活動。譲り受けた和装小物や日本の伝統文化に触れ着物に関心を抱く。